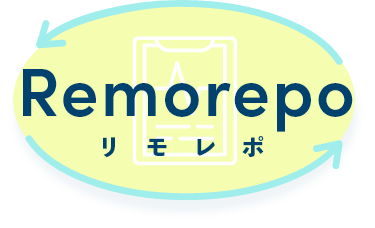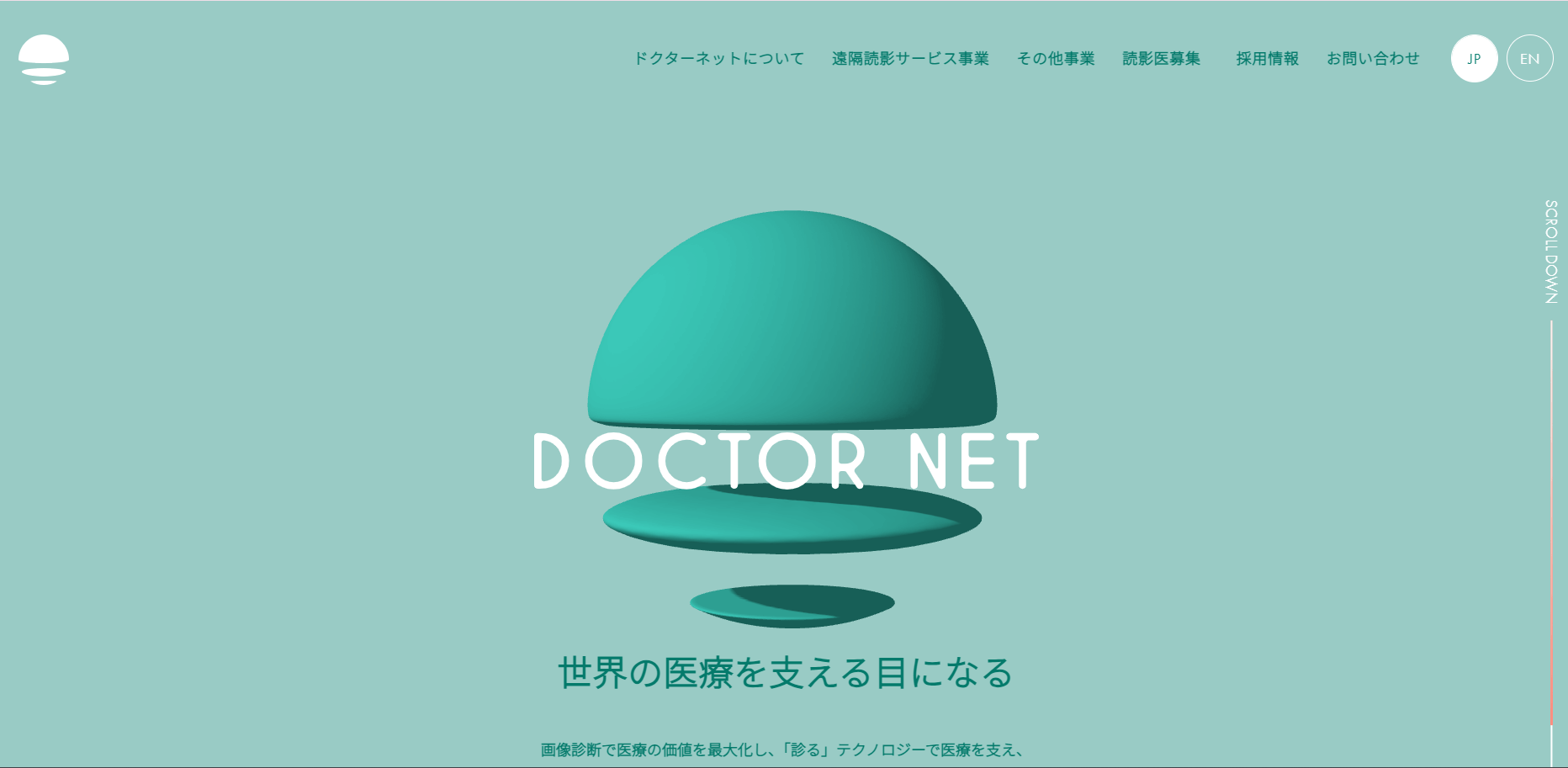AiCT(オートプシー・イメージング)について
AiCT(オートプシー・イメージング)とは
AiCT(オートプシー・イメージング)とは、「死亡時画像診断」を意味します。ご遺体をMRIやCTといった画像診断装置を利用することにより、死因の究明に役立てられています。 従来では死因究明のために解剖などの侵襲性が高い方法が取られていましたが、AiCTを役立てればご遺体を傷つけることなく、死因を診断・究明することに貢献できます。 また、AiCTはご遺体の死因究明だけではなく、小児医療の向上や児童虐待の防止、在宅医療等高齢者医療の向上や、犯罪の見逃し防止、被災者の身元確認など…様々な社会的課題への対応にも有効な策として知られています。 AiCT報告書や鑑定書は、事実に照らし適正に作成されることが求められるため、診断能力を有する医師によって作成されます。
死亡時画像診断を行ったほうがいいケース
児童虐待が疑われる場合
近年、心肺停止状態で病院に緊急搬送された子どもの死因を調査した結果、両親などによる虐待が判明するケースが増加しています。医療者としては虐待の疑いがある場合でも、確信が持てない限り解剖を進められない現状があります。また、病理解剖は遺族の承諾がなければ実施できません。 このような問題を解決する方法の一つとして、AiCTの実施が推奨されています。病理解剖の承諾を求める遺族が加害者である可能性がある場合、画像診断は児童虐待の有無を判断する手がかりとなります。
事件性が疑われる場合
外因死やその疑いがあるような、事件性の可能性が考えられる場合には、AiCTを行った方がいいとされています。例えば不慮の事故や自殺と思われたご遺体であっても、AiCTによる画像診断の結果、他殺である可能性が見つかるケースもあるのです。 他にも、死亡に至った原因が不詳である外因死や、外因による障害の続発症、もしくは後遺障害による死亡などの場合には、死因究明にAiCTが役立ちます。 また、診療行為に関連した死亡のケースでも同様に、AiCTが必要と判断されることがあります。
既往症などがない突然死の場合
特に既往症などがないのに突然死が起きたケースや、病院内でいきなり病態が急変し、なぜ死亡に至ったのかが分からないケースなどにも、AiCTは有効とされています。例えば死因そのものが判明しなくても、行われた医療行為が正当であったかどうか、手術ミスなどが死因に繋がっていないかどうかを確かめる一助となるでしょう。 手術後に急変した症例や、夜間看護師が巡回したときに死亡していた症例などにも、AiCTが活躍しています。
AiCTの実施状況
平成27年度調査研究事業では、死亡時画像診断・AiCTに関する実態調査(※1)が行われました。以下に実態調査に関する内容を解説していきます。
- 調査方法…会員施設にアンケートを郵送またはメールで送付
- 調査期間…平成27年10月1日~11月20日
- 回答率…配布数61施設、回収数46施設、回答率75.4%
AiCTを実施しているか
AiCTを実施しているかどうかについての調査では、「自施設内死亡確認遺体(心肺停止数急事含む)のみ実施」と答えた施設が26%、「自施設外死亡確認遺体(他の医療機関・警察等からの依頼)のみ実施」と答えた施設が13%でした。 自施設内内外どちらのケースでも実施すると答えた施設が22%であり、つまり合計で60%以上の施設がAiCTを利用していることが分かっています。 また、AiCTを利用する病床数別の実施施設割合では、100~199床の施設が36%と最も多く、次に多いのは300~499床の施設25%、次いで200~299床の施設21%となっています。病床の数が多い医療施設ほど、死亡時にAiCTを利用している傾向が見られています。
AiCTに使用するCTの撮影条件と撮影領域
AiCTに使用しているCTの撮影条件や撮影領域について、82%の施設が「診療と同じ条件」で撮影したと回答しています。大してAiCT専用の撮影条件で使用している施設は14%と少数派です。 また、撮影領域は「頭頚部から躯間部の範囲を撮影している」と答えた施設は81%であり、「頭頚部のみ」「頭頚部~膝」と答えた施設はどちらも4%でした。全身を撮影したと回答した施設は11%とされています。 大多数が下肢までの撮影は行っておらず、これは警察などの依頼症例が少ないことと、医師の指示によることに起因していると考えられています。
AiCTの読影は誰が行っているか
AiCTの読影者について、「担当医」と回答したのが46%、「放射線科医」と回答したのが34%となっています。ただしこれは、「自施設内死亡確認遺体(心肺停止数急事含む)」の場合です。 「自施設外死亡確認遺体(他の医療機関・警察等からの依頼)」である場合、「担当医」と回答したのが21%であり、「放射線科医」と答えた施設は11%。「AI情報センターなどの第三者機関」と答えたのは4%であり、その他は「わからない」「未記入」とされています。 自施設内事案の読影の場合、大多数の施設では担当医や放射線科医、もしくはその両者共同で行っていますが、自施設外事案に関しては、担当医や放射線科医の読影は1/3程度で、Aiセンターなどの第三者機関は4%にとどまっていることがわかります。
まとめ
体表検死では情報が限られており、生体とご遺体では血液循環の有無や組織の硬化といった違いがあるため、AiCTを実施する場合には検死に長けた専門医の読影が必要と言えるでしょう。また、病理解剖を行うにしても遺族の承諾が必要であるため、詳しく真相を究明するためにはAiCTが役立ちます。 AiCT報告書及び鑑定書は、誰にとっても適性に作成されないと、遺族や社会の「知る権利」を満たせなくなります。 もしAiCTを行うのであれば、検死に長けている専門医が読影を行う必要があるでしょう。遠隔画像診断に出す場合には、AiCTサービスを行っている専門機関に依頼することも一つの選択肢です。死因究明だけではなく、小児医療の向上や児童虐待防止のためにも積極的な活用が求められています。
遠隔画像診断
サービスの仕組み

重要所見を見落とす主な原因と防ぐ方法を解説しているほか、遠隔画像診断サービスにより重要所見を拾い上げられた事例を掲載しています。