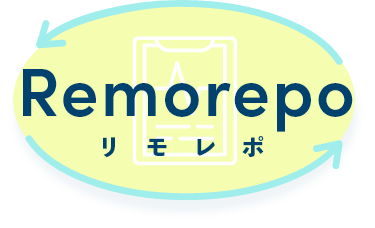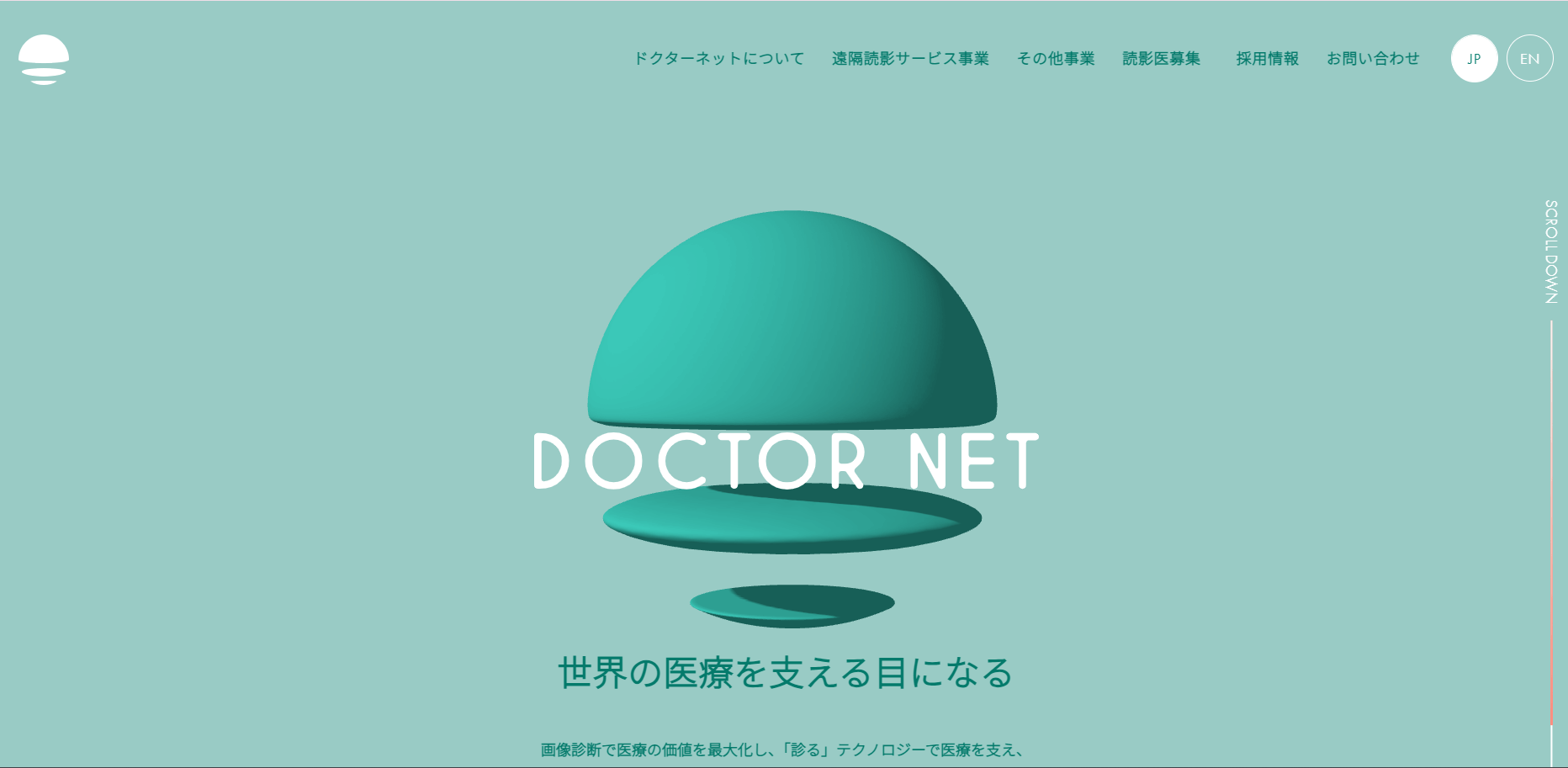脳MRIにおける遠隔画像診断とは?
脳の状態や病気のリスクを把握するための『脳MRI』は、出血や腫瘍といった異常を早期に発見するための検査方法です。脳MRIには専門的な設備が必要ですが、撮影した画像は遠隔画像診断を通じて専門医の診断を受けられます。
ここでは、脳MRIの検査方法や費用、遠隔画像診断で判別可能な病気について解説します。
脳MRIとは
脳MRIの検査方法
脳MRIの検査には、頭部MRI・頭部MRA・頸部MRAの3種類があります。
頭部MRIでは、専用の装置を使用し、磁気を利用して脳を撮影します。頭部MRAは、血管に特化して病変部位を確認するための検査です。
頸部MRAも頭部MRAと同様に、動脈およびその分岐部を撮影して状態を確認します。
MRIやMRAは、MRI装置(磁気共鳴画像診断装置)を使用し、横になった状態で撮影します。脳や頸部の撮影では、息を止める必要がありません。
脳MRIの料金
脳神経外科などで病気が疑われた場合、MRIやMRA検査には保険が適用されます。保険の負担割合に応じて1~3割の範囲で自己負担額が決まります。一般的に、3割負担の場合、費用はおおよそ5,000円前後です。
脳ドックのように、病気の疑いがない場合は健康診断や予防を目的として自費診療が必要です。費用はおおよそ2~7万円程度が相場です。
脳の遠隔画像診断でわかる病気
脳の遠隔画像診断は、医用画像を放射線診断専門医などが読影し、結果を診断します。
遠隔画像診断で判別可能な病気は以下のとおりです。
脳梗塞
脳の血管が詰まり、脳細胞が壊死することで麻痺やしびれ、意識障害、視野の欠損などを引き起こす病気です。大きく分けて、ラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症の3種類に分類されます。
脳腫瘍
頭蓋骨内に発生する腫瘍の総称で、髄膜腫・下垂体線腫・神経鞘腫といった種類があります。脳の中で腫瘍が大きくなると、腫瘍の周りにむくみ(脳浮腫)が生じます。
脳出血
脳の血管が破れて組織内に出血が起こる脳卒中の一種です。主に高血圧が原因となり、それに伴う動脈硬化も血管をもろくするため脳出血を引き起こします。
脳動脈瘤
高血圧や動脈硬化、加齢などが原因で、脳動脈の血管壁が脆弱化し、風船状に膨らむ状態です。
くも膜下出血
くも膜下腔と呼ばれる部位に出血が起こり、血圧上昇、意識障害、嘔吐などの症状を伴う脳卒中の一種です。
もやもや病
脳動脈が狭窄または閉塞し、血流が不足することで発生する病気です。しびれ・脱力・脳梗塞などを発症します。
アルツハイマー病
脳機能が低下し、記憶や思考の能力に障害が生じる進行性の脳疾患です。
脳動静脈奇形
脳内で動脈と静脈がつながってしまい、異常な血管塊が形成される病気です。若年者が脳卒中を引き起こす原因にもなります。
脳動静脈解離
何らかの原因で脳動脈の血管内に出血が起こり、動脈壁が裂ける病気です。脳梗塞やくも膜下出血を引き起こすことがあります。
慢性硬膜下血腫
頭部に外傷を受けた後、1~2か月かけて脳と硬膜の間に血液が溜まり、血腫が発生して脳を圧迫する病気です。
血腫が大きくなると脳を圧迫し、機能低下を招くことがあります。頭痛や手足の麻痺、もの忘れといった症状が現れます。
脳の遠隔画像診断を検討しよう!
脳MRIは、MRIの高精度な画像によって脳や頸部の状態がわかる精密検査です。
撮影した画像は遠隔画像診断により、専門医が患者ごとの状態を診断します。専門医がその場に同席していなくても、画像を撮影すれば本格的な診断を受けられます。
当サイトでは、遠隔画像診断の基礎知識やサービスを利用するまでの流れを紹介しています。以下の関連記事もあわせてご覧ください。
遠隔画像診断
サービスの仕組み

重要所見を見落とす主な原因と防ぐ方法を解説しているほか、遠隔画像診断サービスにより重要所見を拾い上げられた事例を掲載しています。